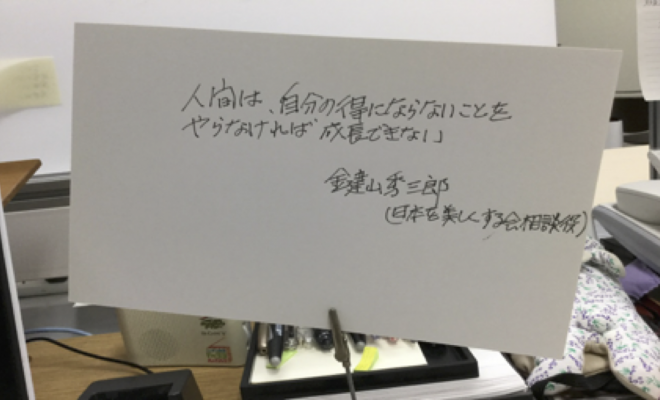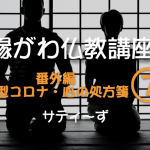第一話 「おたふく風邪と、あ・い・う・え・お」
僕は、小学校3年生まで文字が読めなかった。言葉は喋れるのだが文字が読めなかったのである。
小学校に入学して初めて、その事実を知った。
小学校1年生に入学して一番嫌いな授業が国語だった。何故なら、順番に教科書を読まされるからだ。
担任のM先生は長い定規をもってこちらを指し、「はい、次」と眼鏡の縁を、ひとさし指でずり上げてから私を見詰める。その眼の怖いこと…。
次は自分の番だと思って、こころがキュンとなっているところに「はい、次」の声は、死刑宣告を受けているようなものだ。
たまったものではない。
何もできない自分。ただ佇んで、時間が過ぎることだけを願う自分。いや、思考を停止させる。思考を止めなければ、惨めさや悲しさが一気に自分を押し流しそうな感じがしてくる。
ぐっと教室の板床に踏ん張って立ちすくんで、その場から流されるのを避けているような感覚が、全身を駆け巡る。その時間は、7~8秒くらいだろうか。「はい、次」の声とともに椅子に座る。教科書の陰に隠れるようにして、手のひらの指を折りながら心の中で数える。「いち、にい、さん、し…」。それしか、ちいさな僕にはできなかったのである。
そんな僕が、まともに本を読めるようになったのは小学校3年の始めの時だったと思う。「海底二万里(かいていにまんり・かいていにまんまいる)」を手にしたことを、やけに覚えているのだ。確か、夏休みか春休みの宿題で本を読むことになり、図書館で手にしたのが「海底二万里」だった。何故、その本を選んだかまでは記憶にはない。表紙のイラストにこころがひかれたのかもしれない。
今では分からないけど、小さな僕の自尊心は、大きくなった時、「小学校3年まで本が読めなかった僕が、初めて読めた本が『海底二万里』だったんだよ」と、誰かに自慢げに話すことによって、小さく傷ついた自尊心を慰めたかったのかもしれない。だから、本のタイトルだけは忘れなかったのかも。
じゃ、何故、読めるようになったのか?それは、母親のお蔭である。
おたふく風邪で学校を何日か休んだ時、母親が、ひらがなの一覧表を壁に貼り、ひとつひとつ教えてくれたのだ。「あ・い・う・え・お・か…」と母親が、順番に一文字一文字指さして読み、教えてくれる。僕は、「あ・い・う・え・お」と話すことはできるが、たった一文字を指されて「これは?」と訊かれると、「あ」から始まって、その文字までに辿りついて、ようやく答えることができる始末であった。
当時の借家の薄暗い部屋のなかに、小さな窓から差し込む光に部屋の埃が舞っているのが視覚的イメージとして残っている。そして、顔はハッキリと思い出せないのだが、差し込む光の逆光で全体が真っ黒な母親の姿が思い出される。この思い出は、母親との思い出の中で真っ先に思い出される大切な出来事だ。
当時、4人姉弟のバッチ(一番下)の私。母親は、収入の無い父の代わりに現金を得るために働き通しだし、姉の面倒もあり、私と2人きりで時間を過ごすことなどなかったのである。この時の幸せは、おたふく風邪のお蔭だ。
現在、老人施設でお世話になっている母親は、寝たきりで声を発することが無い。それだけに、その時の母親の声のイメージを追い求めるが思い出せないし、耳には響かない。晩年、ご宝前に向かいお経をあげ、亡くなった父に、「お父さん、ありがとう」という声は耳に残っている。が、僕だけの声が欲しかったと、少し悲しい思いをしている。
しかし、その小さく傷つく自尊心と小さな幸せの物語が、その後の僕の人生の物語を創り上げていくのだから面白い。小学校3年の時、「本読みのビックバン」が起きたのだから。